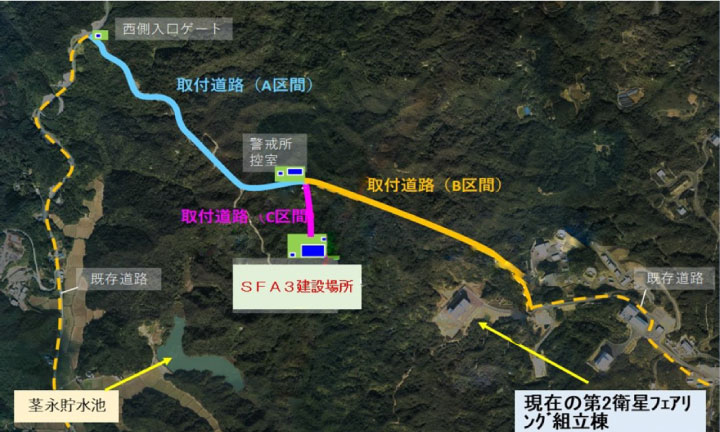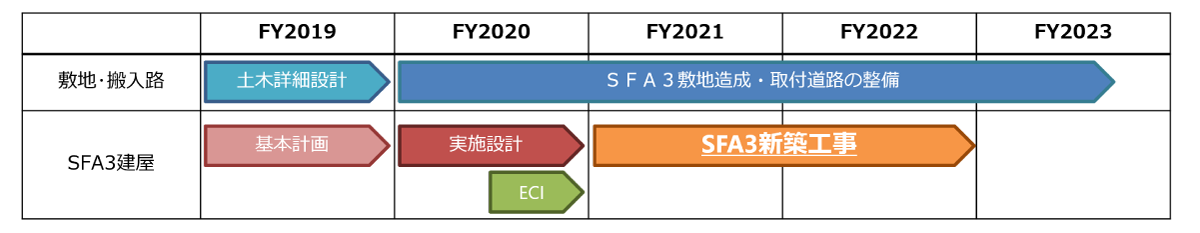高度化する打ち上げに対応し、複数の人工衛星・探査機を同時に組立て整備できるようにするため、現在の衛星フェアリング組立棟(SFA)、第2衛星フェアリング組立棟(SFA2)に次ぐ、新たな衛星組立棟である第3衛星フェアリング組立棟(SFA3)を整備することとなりました。
建設地を射点から3km以上離れた位置に設定することにより、打ち上げ時においても退避等の制限がかからず、人工衛星・探査機の組立て等作業が可能となることから、年間の打上回数の増加、ひいては国際競争力の向上に貢献することが可能となります。
JAXAとしては過去最大級規模の計画を立案・実行し、無事2023年4月に完成しました。
概要
- 構造・階数:S造+SRC造・3階
- 建築面積:4408.10m2
- 延べ面積:5772.70m2
工事経過
2021年
- 5月:着工
- 11月:鉄骨工事開始
2022年
- 2月:鉄骨工事終了
- 5月:内装開始
- 11月:内装終了
- 12月:クレーン、消防、建築検査
2023年
- 1月:ガス検、インターロック電源、監視操作盤制御確認
- 2月:騒音、清浄度、温湿度測定
- 3月:連続温湿度測定