

研究とプロジェクトの二刀流現場の課題を研究で解決へ導く
丹羽 智哉
2010年入構
工学研究科 機械理工学専攻修了
環境試験技術ユニット
REASON入構の理由
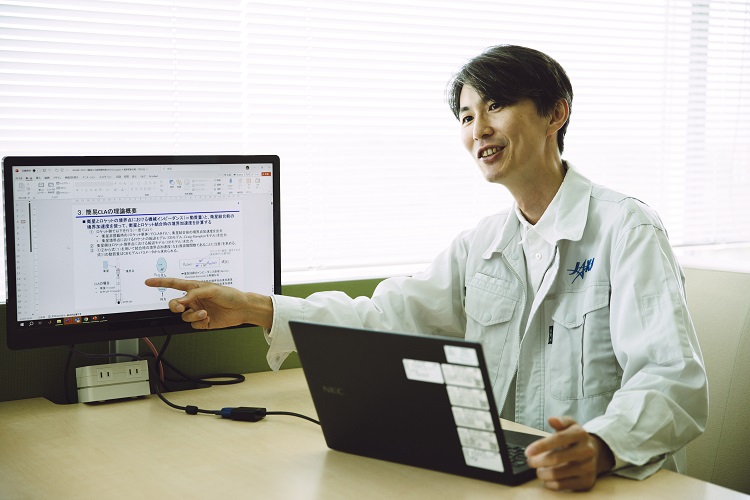
ポジティブ思考で個性を見出す
好きな映画は『アポロ13』です。この映画では、アポロ13号で起きた爆発事故から宇宙飛行士を救おうと地上で技術者たちが奮闘する姿が描かれています。寄せ集めの道具を組み合わせて、宇宙船で起きていることを再現するシーンを見て、私も道具に触れながら何か問題を解決するようなことをやってみたいと思うようになりました。
大学は機械系の学科に進み、ロボットや機械学習の研究をしました。卒業後の進路を考えたときに、周囲に流されずに私が邁進できるのは昔から好きな宇宙だと考え、宇宙にかかわる仕事を目指しました。宇宙業界を志望する学生のなかには、やはり宇宙に関連する研究をしていた人も多くいます。当時私は宇宙については全くの素人でしたが、前向きに捉えれば今から何にでも挑戦できるポテンシャルがあるとも言えるはず。そう考えて、宇宙を軸に幅広いプロジェクトに携われるJAXAを就職先として選びました。
WORKわたしの仕事

衛星開発は究極の物づくり
人工衛星の仕事は、ロケットで宇宙に打ち上げられて軌道上に到着してからが本番です。5年、長いときは10年にもわたって運用します。それにもかかわらず、一度宇宙に行くと、壊れても直しに行くことはできません。これほどのドキドキ感がある物づくりは、地上にはないでしょう。研究者・技術者として試されているかのような感覚に惹かれて、衛星開発にかかわる部署を希望しました。
最初に配属されたのは、環境試験技術ユニット(当時は環境試験技術センター)でした。宇宙機の振動試験や音響試験などの環境試験に関する研究と筑波宇宙センターにある環境試験設備の維持・更新などを行いました。入構4年目からは、「だいち2号」の開発にも併任という形で参加することになりました。実際に打ち上げるフライトモデルがすでに出来上がっていて、ちょうど環境試験が始まるタイミングでした。環境試験技術ユニットでの研究の成果を試験に活かせましたし、試験に立ち会った経験を研究に活かすこともできました。
だいち2号が打ち上がった翌年、入構6年目からは「だいち3号」を開発するプロジェクトチームでの仕事が本務となり、環境試験技術ユニットでの研究は併任という形をとって続けることになりました。私が担当したのは、だいち3号の構造設計です。衛星の構造を設計することは、振動への耐久性を持たせることと繋がっています。衛星は足が地面についているわけではないので、軌道を維持するために装置を動かしたり、太陽光パネルの方向を変えたりするだけでも揺れてしまいます。カメラで写真を撮るときに手ぶれが起きるように、衛星も揺れると撮影する写真にぶれが生じてしまいます。衛星の構造設計には、一生の悩みである振動を抑える工夫が必要なのです。環境試験技術ユニットで「振動」をキーワードに衛星のセンサや構造の研究をしていたことから、だいち3号の構造設計に挑戦することになりました。
結果的に、だいち3号の打上げは失敗しました。失敗したとわかったときは、ショックのあまり崩れるように机に突っ伏してしまいました。今でも残念に思う気持ちがあり、完全に立ち直れたわけではありませんが、次のプロジェクトに向けて走り始めている仲間を見ると、私も落ち込んでばかりではいられないと思わされます。現在は環境試験技術ユニットが本務となり、振動の研究と筑波宇宙センター内の環境試験設備の維持・更新を行っています。JAXAの宇宙機のプロジェクトから振動の解析手法や振動試験の方法について相談や支援の依頼が来ることも多く、色々な宇宙機の開発に携わっています。
FUTURE将来の想い
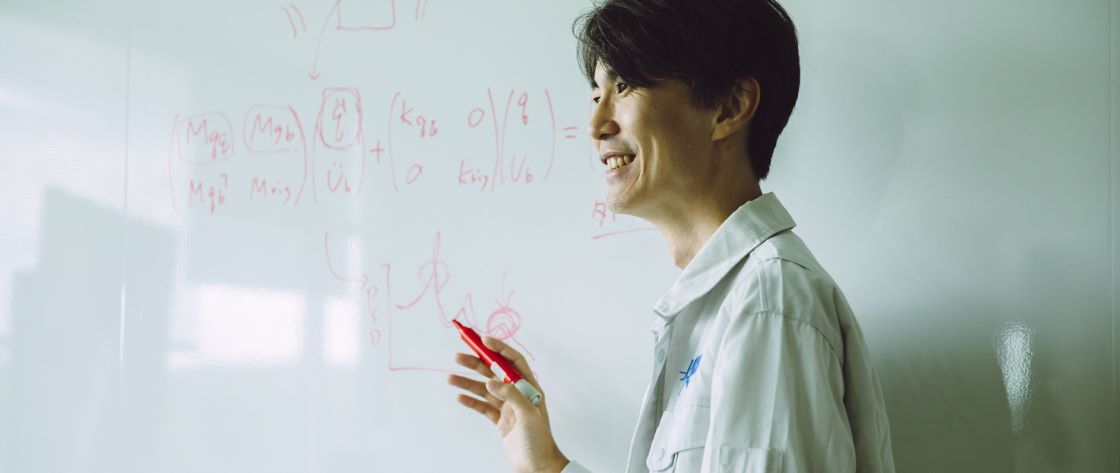
研究とプロジェクトの二刀流で 強みを磨く
研究かプロジェクトでの業務のどちらかを行うのではなく、その両方を同時に進めていくことが理想です。こう思うのは、やはり振動の分野の研究は、開発や運用の現場での困りごとを解決してこそ意味があるからです。困りごとの本質を理解できなければ、研究は進められません。だいち3号の開発を通じて、現場で出てきた課題やメーカーの皆さんが抱えていた外からは見えないモヤモヤを拾い上げて、研究テーマにして、次の衛星プロジェクトでは同じことで困らないようにするサイクルを回していくことが大切だと思いました。
だいち3号のプロジェクトへの異動が決まったときは、振動の研究を続けられるようにプロジェクトマネージャに相談して、環境試験技術ユニットと併任できるように調整していただきました。もちろん研究は併任しなくても続けられますが、併任という形をとって本務で研究を行っている部署との繋がりを持ち続けたかったからです。やはり研究が本務のコミュニティのなかにいると、周囲の研究の進み具合が横目で見えて、それが研究を続けるモチベーションになります。何気なく疑問に思ったことも気軽に話せますし、同僚からの「それいいね」の一言が新しい研究テーマを立ち上げる後押しにもなります。研究とプロジェクトの両方の業務を両立させながら、私の柱である「振動」の分野をこれからも究めていきます。
CAREER PATHキャリアパス
入構してからこれまでのキャリア
-
1st year
環境試験技術センターに配属
現・環境試験技術ユニット。宇宙機の振動試験や音響試験などの環境試験に関する研究と筑波宇宙センターの環境試験設備の維持・更新を行った。
-
4th year
衛星利用ミッション本部ALOS-2プロジェクトチームに併任
だいち2号の機械・構造系の開発、ロケットインタフェースの調整などを担当した。
-
6th year
第一宇宙技術部門 衛星システム開発統括付に配属
だいち3号プロジェクトの前身にあたるプリプロジェクトチーム員として、プロジェクトチーム化に向けた業務を行った。環境試験技術ユニットも併任し、振動についての研究を続けた。
-
7th year
第一宇宙技術部門先進光学衛星プロジェクトチームに配属
振動についての研究の経験を活かして、だいち3号の衛星システムとミッションセンサの開発を行った。
-
14th year
環境試験技術ユニットに配属(現職)
宇宙機の機械・構造系の試験検証技術の研究開発を行う。JAXA宇宙機一般試験標準機械系試験WGのサブリーダーを務める。JAXAの色々な宇宙機の開発に携われるのがやりがい。

THE OTHER SIDE OF THE MOON私の一面
社会人になってキャンプにハマり、毎年やっています。テントを張ったり、火を起こしてご飯を作ったり、キャンプは意外とやることがたくさん。作業に没頭していい具合に身体が疲れると、夜はぐっすりと眠れてリフレッシュできるのがキャンプのいいところです。