

23
有人宇宙システムと向き合う四半世紀
次世代へと紡ぐ宇宙探査の未来
永井 直樹
1994年入社
理工学研究科修了
国際宇宙探査センター 事業推進室
REASON入社の理由

安全に宇宙に行ける技術を求めて
初の日本人宇宙飛行士の誕生で、そのような職業もあるのかと漠然と思っていたところ、高校生の時(1986年)にスペースシャトルチャレンジャー号の事故に衝撃を受け、「安全に宇宙に行けるようにしたい」、という想いが芽生えました。
大学では伝熱工学を専攻しました。宇宙機の大気圏再突入時に発生する衝撃波に関する流れの研究をしていました。実はその当時、大学の近くに筑波宇宙センターがあっても一度も見学に行ったことはなく、JAXAへの関心も漠然としたものでした。しかしちょうど就職を控えたころ、1984年からその構想が始まった、「宇宙飛行士が安全・快適に宇宙空間で活動することができる」宇宙ステーションプロジェクトに日本もチャレンジしていることを知り、「自分の想いを実現できる場所はJAXAしかない」、と明確に思い至りました。
WORKわたしの仕事

多様な考え方をぶつけて 一歩前に進めるアイデアに繋がる
入社4年目に念願は叶い、日本で初となる「有人宇宙システム」を開発する部署に配属されました。国際宇宙ステーション(ISS)の日本実験棟「きぼう」の開発はまさに未知への挑戦でした。当時、20・30代だった我々JAXA開発チームは、検討した設計や安全制御の方策をNASAへ説明に行っては、アポロ計画にも携わった百戦錬磨の開発者から「全くなっていない」と何度も何度も突き返されていました。ダメ出しが繰り返される中で、有人システムの考え方そのものを学んでいったのです。
また、国際共同プロジェクトであるISSは各国の構造物が連結されるため、その設計や安全基準を守る方策は協働して検討するのですが、国によってそのアプローチが異なるため、意見が真っ向からぶつかることもありました。例えば火災防止設計では、米国は飛行士の関与を最小限とすべく、火災が発生する要素を徹底的に排除すべき、というのに対し、ロシアは人間が搭乗することを前提に、飛行士が関与して安全に消火させる方法も積極的に取り入れるべき、という具合です。この有人宇宙大国との議論の中有人宇宙開発経験の浅い日本は、当初は大人の中に子供が入っていくような感覚でした。それでも日本人の物づくりの緻密さや細部にわたる配慮をした設計・製作アイデアを粘り強く提案し続けるうちに、やがて少しずつ受け入れられるようになりました。どの技術もそれを担っているのは人であり、多様な考え方をぶつけることで一歩前に進めるアイデアに繋がることを、これらの経験から学びました。
「きぼう」が完成してようやくスペースシャトルに搭載されて打ち上げられ、宇宙に設置されたときはまさに感無量でした。その場にいたNASAのプログラムマネージャから、「日本も有人宇宙開発の(本当の)仲間になった」と言われたことを誇らしく感じたと同時に、これまで共に「きぼう」を完成させた仲間の顔がたくさん思い浮かびました。JAXAのメンバーを始め、担当する企業の方々、NASAの熟練メンバー、海外宇宙機関のエンジニアたち…本当に多くの方たちと協働しました。それぞれの視点で、どうすれば適切なものとなるのか、より良いものとなるのか、熱意をもって取り組み、一つのものを作り上げる。そのような熱を肌で感じながら活動した経験は、今でも仕事に取り組む際のエネルギーとなっています。
現在は将来の有人宇宙探査である国際プロジェクト「アルテミス計画」の下、これまでの地球周回から月・火星での活動に軸足を置いたプログラムを企画し、ミッションの立ち上げを進めています。新しいことが始まると、これまでとは違った分野の研究者やエンジニアと出会う機会に恵まれます。その方たちと議論し、より良いミッションに仕立て上げていく時間は、未来に向けてのワクワク感を感じるところで、本当は一エンジニアとして自分が担当したいと思うところではあります。立場上なかなかそうもいかないのですが。
FUTURE将来の想い

次なるミッションへ 月・火星へ人類は飛躍する
これまで有人宇宙活動に関わり、次の大きなステップとなる国際宇宙探査では、月・火星のミッションを立ち上げる機会に恵まれました。自分が生まれた年に人類初の月面着陸が実現し、そして時を経た今、新たな段階、月・火星への人類の飛躍を目指した活動が開始しています。この機会を確実なものとすべく、使命を着実に果たして行きたいと感じています。
宇宙開発は、今大きな転機にさしかかっています。宇宙でできることはこれからも広がり続けます。多種多様な専門を持った方々と一緒に議論し、一つの企業や国だけでは達成できないような大きな目標を一緒に作り上げることができます。これまでに得た経験と知識をフル活用して、時には一つの世代ではできないくらい壮大な目標の実現を、一緒に担ってみませんか?
CAREER PATHキャリアパス
入社してからこれまでのキャリア
-
1st year
技術研究開発本部試験部に配属
衛星の打上前の環境試験(真空・太陽光・温度を再現するチャンバ)や試験設備開発を経験する。設計図の見方、解析条件の設定、検証試験の実施、宇宙機の運用と開発の基礎となるスキルを得た。
-
4th year
国際宇宙ステーション日本実験棟(JEM:Japanese Experiment Module))開発プロジェクトに配属
船外モジュール及び衛星間通信システムの開発等を担当、有人宇宙システムの設計、安全要求の理解と国際プロジェクト遂行に関して隅々まで知識を得た。
-
13th year
ヒューストン駐在員事務所(NASAジョンソン宇宙センター)
日本とNASA シャトルプログラム/ISSプログラム間の技術及びプログラム調整の仲介役。アポロ計画から続く、NASA等の仕事の仕方を学ぶとともに、様々な異常事象発生時の技術的な調査とプログラム的な交渉機会を得た。JEM全便の打上、宇宙ステーション補給機「こうのとり」(HTV)初号機の打上調整に従事。海外機関のメンバーとの人脈を得ることもできた。終了間近のシャトルプログラムの動向に気を配りながら、「きぼう」や「船外モジュール」が確実に打ちあがるよう尽力した。
-
17th year
有人宇宙技術部門宇宙環境利用センター、有人宇宙技術センター(利用/運用計画担当)
日本実験棟「きぼう」で行われる利用ミッションを実行に移すための利用/運用計画の調整(国内/国際)を担当する。「きぼう」を最大限使い尽くすことを目指し、利用/運用計画調整を実施、ヒューストンでの人脈が大いに役立った。
-
24th year
有人宇宙技術部門事業推進部(計画マネージャ)
有人宇宙技術部門の事業推進に係る計画立案調整、予算調整、政府調整、ISS/HTV/日本人飛行士ミッションの危機管理対応、ISSプログラム副プログラムマネージャを務める。
-
26th year
国際宇宙探査センター事業推進室長を務める
国際宇宙探査(月、火星)に関する計画立案調整、予算調整、政府調整、プロジェクト立ち上げに携わる。
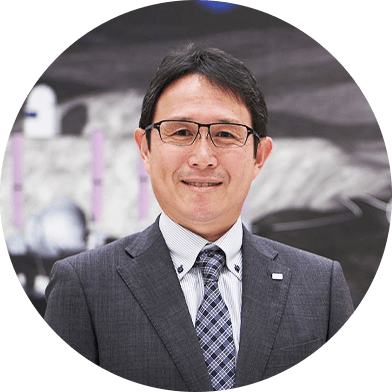
THE OTHER SIDE OF THE MOON私の一面
学生時代からオリエンテーリングに励んでいます。コンパスと地図を携え、進むコースの計画と実行はその場で行い、ゴールまでの全速力で駆け抜けタイムを競います。過去には本場欧州の大会にも出場。今でも競技への参加の他、競技会運営を行ったりしています。