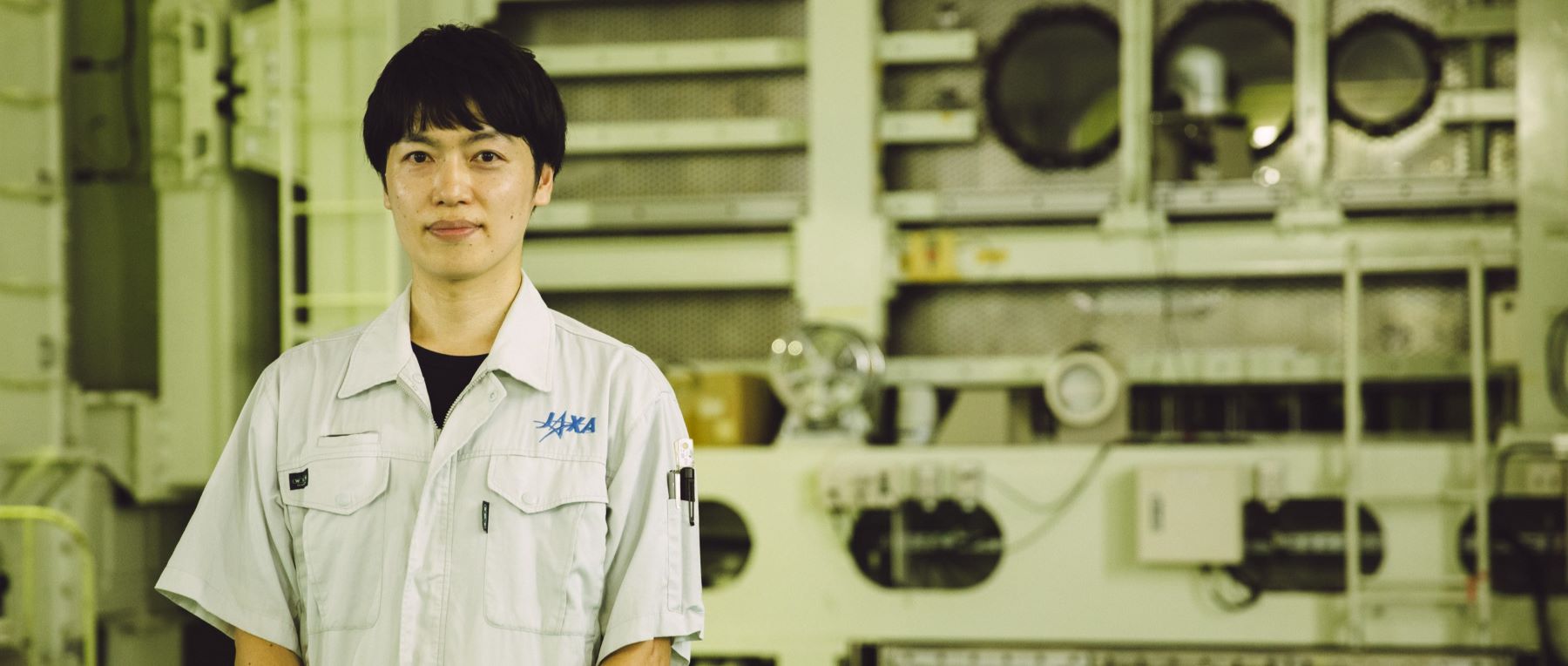

航空・空力分野で持続可能な社会への貢献と新たな移動の価値創造
古賀 星吾
2010年入構
工学系研究科航空宇宙工学専攻卒
航空技術部門 航空環境適合イノベーションハブ
REASON入構の理由

まだ世にない新しい乗り物の開発を目指して 航空宇宙の世界へ
子どもの頃、星を見るのが好きで宇宙に興味を持ち、図鑑を見てよく星座の絵を描いていた記憶があります。建築士の父が図面を描いているのを見たり現場に連れられ測量を手伝ったりすることもあり、設計して何かをつくることにも関心がありました。宇宙に行きたいという気持ちと何かを作りたいという気持ちから誰でも宇宙に行ける乗り物をつくりたいと思うようになりました。
大学では航空宇宙工学を専攻しました。学部3年生の夏休みは、アメリカの砂漠で空き缶衛星を小型のロケットで打ち上げてもらい、地上のゴールを目指すARLISSの大会に参加し、国内大会では良い成績でしたが、アメリカでの本大会では数々のトラブルでうまくいかずに悔しい経験をしました。他にも室内飛行ロボットコンテストに参加し、面白いアイデアの機体をメンバーと一緒に考え作って飛ばす楽しい経験をしました。
研究室では音速の5倍以上の速さで飛行する極超音速旅客機の研究に取り組みました。今の飛行機では日本からアメリカ西海岸まで約10時間かかりますが、極超音速旅客機ではわずか2時間で飛行できます。この技術は、地上から宇宙へ物資を運ぶ輸送システムの開発にも応用でき、極超音速旅客機の最適設計を学べる研究室を選びました。
大学院を修了した後も極超音速旅客機のようなまだ世の中にない新しい乗り物の開発に携わりたいという思いが強くありました。メーカーやエアラインなどの実際の機体に近いところにも惹かれれるところはありましたが、JAXAなら未来を見据えた研究開発ができるだろうと考え、就職先として選びました。
WORKわたしの仕事

空力研究と社会実装 創意工夫で実験して、現象を理解し、社会に役立てる
入構時、はじめは風洞技術開発センター(現・設備技術研究ユニット)に配属されました。風洞とは人工的に風をつくり出す設備です。航空機や宇宙機の研究開発では、風洞で模型に風をあてて、力や流れの計測を行います。学生の時は、既に取得された試験データを設計に使う側でしたが、試験データを取得する側になって、風洞の奥深さを知りました。現在に至るまで、実験でデータを取得し検討する仕事をしていますが、一般的な風洞試験だけでなく、少し変わった特殊な試験も実施してきました。
担当した風洞試験の中で印象深いものの1つは、国際宇宙ステーション(ISS)から物資を回収する「HTV搭載小型回収カプセル」の自由回転風洞試験です。カプセルが大気圏に再突入して、減速しながら降下する過程で、遷音速と呼ばれる、音速付近の速度域になりますが、動的に不安定になってカプセルが大きく振動してしまう可能性があります。最悪の場合、パラシュートが開けず回収できない恐れがあるので、風洞試験だけでなく数値解析(CFD)や自由飛行試験の他の手法の担当者と連携して検討を行い、ミッション計画に重要なデータや情報を提供するとともに、動的安定性の現象に関する知見を深めました。
カプセルが無事に回収され、ミッション達成の知らせを聞いたときは少しでも貢献できたことを嬉しく思いました。
現在は、主に、航空環境適合イノベーションハブにおいて、「リブレット」と呼ばれるサメの肌をヒントにした微細な溝列構造で、空気抵抗の内の摩擦抵抗を軽減する技術を研究開発しています。エアラインやメーカーの皆さんと協力しながら、航空機に適用して、燃費改善および二酸化炭素排出削減により環境への負荷を減らすための活動をしています。
FUTURE将来の想い
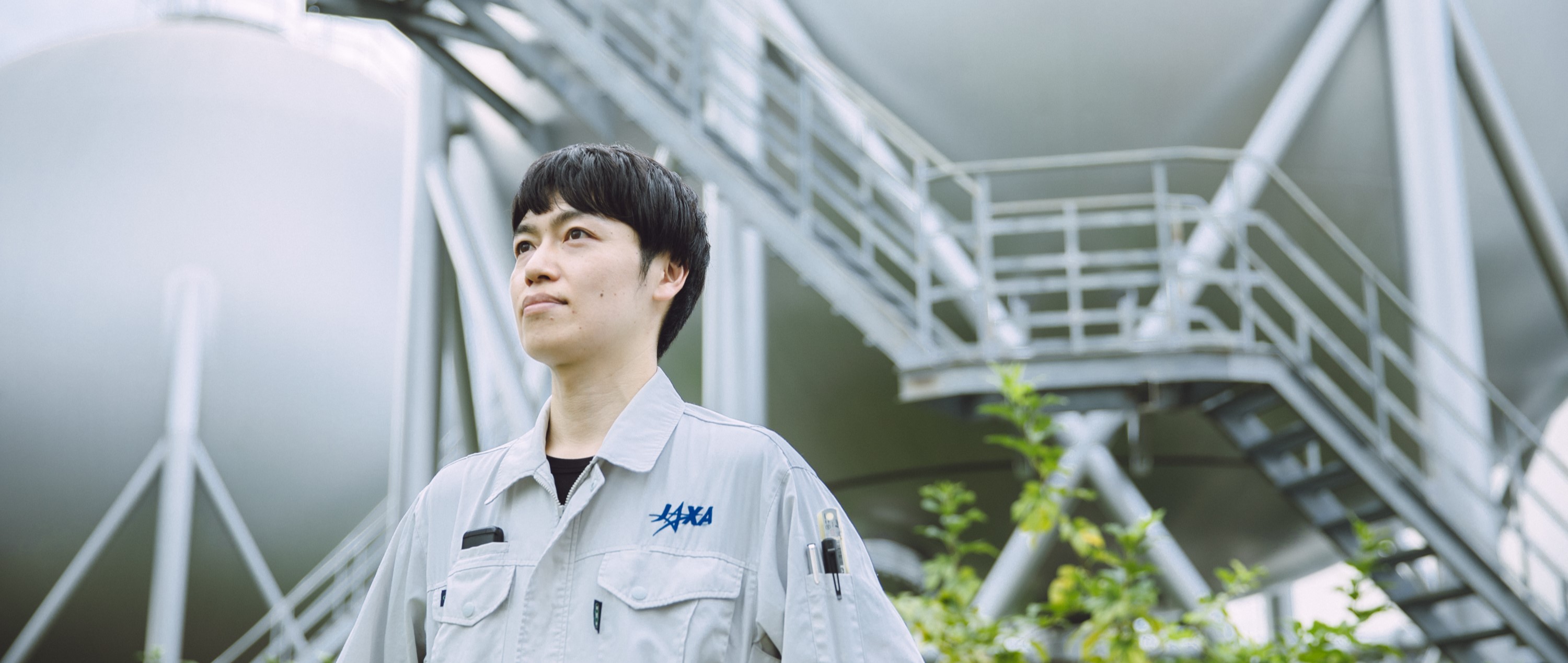
航空の可能性の追求 まずは環境改善、そして、新たな輸送システムの実現
直近の目標はリブレットの社会実装を進めて地球の環境を良くし持続可能な社会に貢献することです。その先は、やはり極超音速旅客機や高速二地点間輸送(P2P)、宇宙往還機などの研究開発に携わりたいという想いもありますし、現在の移動をもっと楽にしたり価値あるものにしたりすることにも関心があります。
これまで航空宇宙分野と直接関わっていなくても、「世の中の課題を解決したい」「新しいものを創造したい」「ひとつのことを探求したい」という気概と実行力があれば、JAXAは自分のやりたいことができる環境が整っています。ぜひ一緒に面白い仕事をやりましょう!
CAREER PATHキャリアパス
入構してからこれまでのキャリア
-
1st year
研究開発部門 風洞技術開発センター(現・航空技術部門 設備技術研究ユニット)に配属
風洞天秤の開発、様々な模型や風洞を使った試験を行った。
-
7th year
航空技術部門 事業推進部(企画ライン)
部門内の基盤研究の研究管理や設備の維持管理、部門外および機構外との連携・調整などを行った。研究業務からは離れてしまうものの、部門全体の研究を知る機会となった。
-
9th year
航空技術部門 空力技術研究ユニット
多分野統合基盤システムの研究開発の中で、航空機タイヤからの水跳ね予測技術の研究開発を行った。数値解析の担当者と連携して試験を実施し検証データを取得した。風洞は使わず、スポーツ中継などに使われる高速レールカメラを活用して試験した。
-
15th year
航空技術部門 航空環境適合イノベーションハブ(現職)
リブレットの抵抗低減性能を評価する風洞試験や実機に適用した際の効果推算を行っている。

THE OTHER SIDE OF THE MOON私の一面
子どもが生まれる前は、JAXAのチームでサッカーしたりロードバイクで少し遠出したりしていました。最近は子どもと近所の公園や動物園に行って遊んで過ごしています。